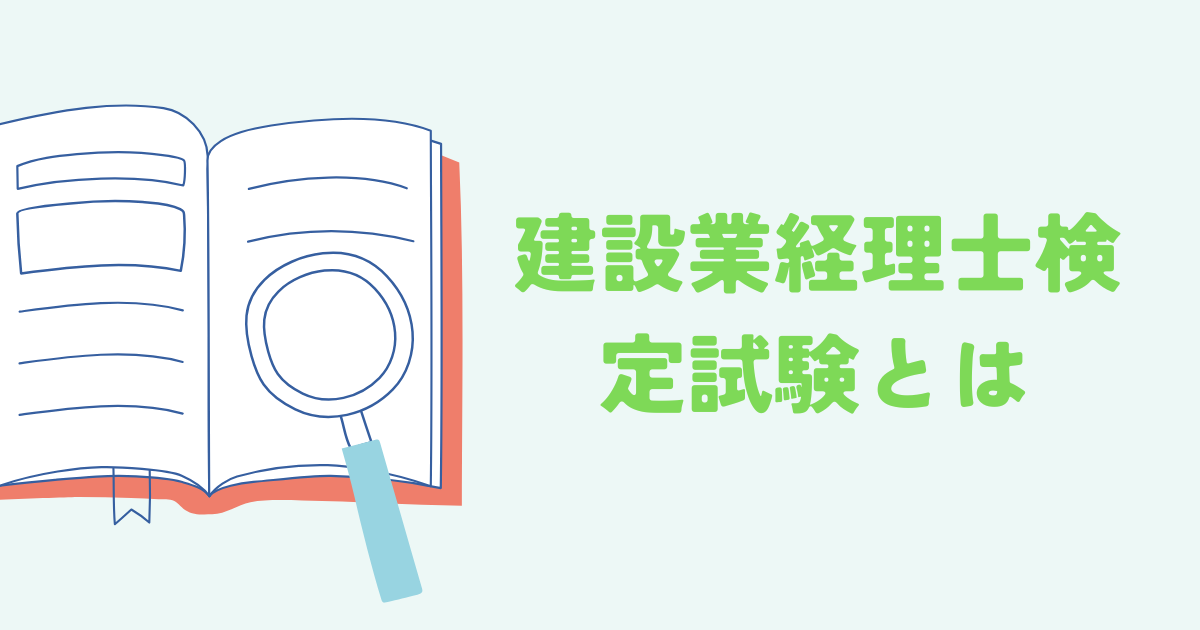「建設業経理士って難しいの?」「どの級から取ればいいの?」
そんな疑問に答えるため、筆者の実体験をもとに本記事では建設業経理士1級・2級の難易度・合格率・勉強時間を、実際の試験データをもとにわかりやすく解説します。
また、資格保有者がどのように仕事に活かせるのかも併せて紹介します。
建設業経理士検定試験とは?日商簿記検定との違い
建設業経理士検定とは建設業に特化した簿記会計の能力を証明する資格となります。筆者の体感になりますが2級は日商簿記検定2級と8割くらい出題範囲が一緒。1級は6割くらい出題範囲が同じです。ただし両方とも日商簿記検定1級の方が難しいです。建設業に特化した簿記とは建設業の実務で使用する原価計算書の作成や経営事項審査という建設会社の経営能力などを点数化したものの理解を問う問題が出題されます。また、完成工事高や完成工事原価など日商簿記検定では聞かない勘定科目を使用します。ちなみに前者が売上高、後者が原価になります。大きな共通点や相違点をまとめると以下になります。
共通点
・複式簿記の知識を問う
・貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の主要財務諸表を作成できる・読む為の知識を習得できる
・企業のお金の流れ、会計に関する知識を学べる
相違点
・連結会計や株主資本変動計算書など一部の論点が建設業経理士検定試験では出題されない
・原価計算書の作成や経営事項審査に関する知識を問われる
・2級以上は経営事項審査で加点がもらえる
ほかにも科目毎の合格を建設業経理士検定試験は認めていたり、科目合格に有効期限が設定されているなどの違いがあります。
建設業経理士2級はコスパ最強の資格
上記の相違点を踏まえて、建設業経理士2級は、
- 基礎的な簿記知識があれば数か月で合格可能
- 簿記未経験でも1年以内に十分合格を狙える
- 合格率は 30〜50%前後 と比較的高め
コスパと即効性のバランスが取れた資格です。
簿記2級に近い内容で、建設業界特有の「原価計算」や「工事収益認識」を扱う点が特徴ですが、試験範囲は日商簿記と比べると狭く、出題される問題も基礎問題が多いです。また、試験出題パターンがある程度決まっている為、過去問を繰り返しすることでパターン別の解き方のロジックが理解できるようになります。
建設業経理士試験の難易度・合格率・勉強時間
| 級 | 合格率(目安) | 特徴 |
| 1級 | 財務諸表・財務分析:約20%/原価計算:約10% | 科目合格制(5年有効)、独学でも合格は十分に可能 |
| 2級 | 約30〜50% | 社会人に人気・独学でも合格可能 |
学習時間の目安
私自身2級合格後1級を受験しましたが、通常の実務必要な知識は2級で十分だと感じてます。もちろん、今後経営管理やさらに深い知識を武器に経理のスペシャリストを目指すのであれば1級受験も視野に入れてもいいと思います。日商簿記2級保持者の私が建設業経理士検定試験2級を合格するのに100時間ほど勉強しましたが、1級は2級合格後+500時間ほど独学で勉強しました。
上記の通り1級は2級に比べ試験範囲や難易度がグンと上がる為、長期的に勉強時間を確保するのが必要になります。ただし1級には科目合格制度があり1科目ずつ受験してもOKなので、1科目ずつ時間を掛けて学習するのがおすすめです。
まとめ:
建設業経理士検定試験は実務+経営事項審査への評価点で建設業従事者にとって価値の高い資格。
・実務に必要な知識のほとんどは2級で十分
・実務と直結した実践的な資格
・独学で十分合格が狙える